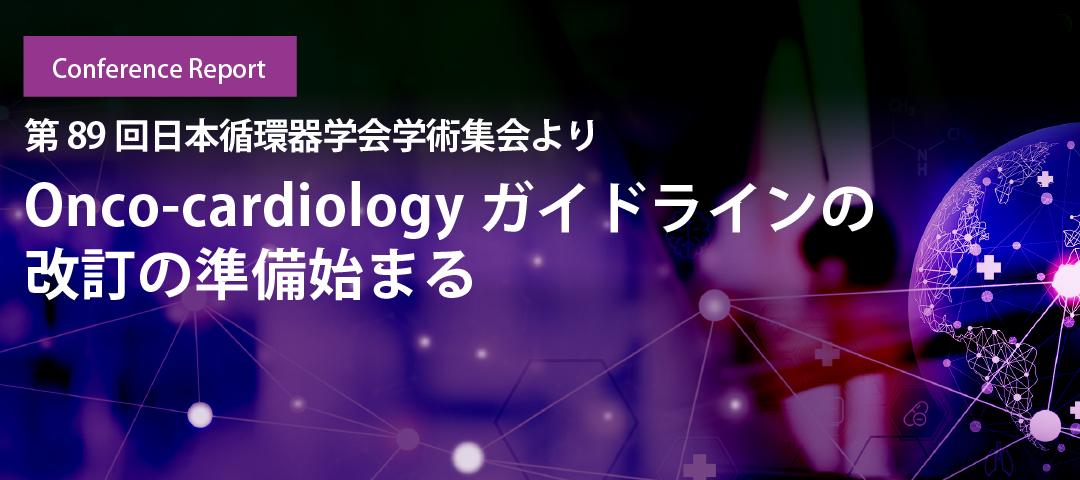第89回日本循環器学会学術集会(会長:名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学講座循環器内科学・室原豊明教授)が3月28日から3日間にわたって横浜で開催された。3日目にシンポジウム18『循環器医が知っておくべきがん治療における心血管毒性のマネジメント~Onco-cardiologyガイドラインより』が開催された。
腫瘍循環器に関する診療ガイドラインとして日本臨床腫瘍学会と日本腫瘍循環器学会が中心となり、2023年3月に『Onco-cardiologyガイドライン』が刊行されたことは、本サイトでも紹介している。シンポジウム18は、そのガイドラインのとりまとめの中心となった東京慈恵会医科大学腫瘍・血液内科の矢野真吾教授と東京大学大学院医学系研究科循環器内科学の赤澤宏講師(本サイトの編集委員)が座長となって企画された(写真)。
2023年のガイドラインは本邦で初めて刊行された腫瘍循環器に関する研究と診療のガイドラインであったが、エビデンスの蓄積の乏しさを表明する異色のガイドラインとなった。その後の研究成果の蓄積や診療体制の整備状況を反映したガイドラインの改訂が待たれているが、赤澤講師によると「現時点では改訂に向けたブレインストーミングが関係者の間で始まった段階」とのことだ。また矢野教授は、「2年後の改訂を目指して準備を進めたい」と本サイト記者に語った。

アントラサイクリン系心筋症に対する早期介入の重要性
シンポジウムのトップバッターとして登壇した東京慈恵会医科大学附属第三病院腫瘍・血液内科の郡司匡弘医師は、アントラサイクリンの心毒性のマネジメントについてこれまでの報告をレビューした。
アントラサイクリンは放線菌から見出されたダウノルビシンなどが急性白血病に著効することが発見された1964年から抗がん剤としての臨床応用が開始され、分子標的治療薬が、がん薬物療法の中心になった現在でも悪性リンパ腫や乳がんの治療では、なくてはならないキードラッグとなっている。
2022年に公表されたESCガイドライン(ESC Guidelines on Cardio-Oncology)でもアントラサイクリンの使用に際しては心筋症の早期発見と早期介入の重要性が強調され、①治療開始前に心電図や血液バイオマーカーを計測してベースラインを確認しておくこと、②治療開始後の定期的なモニタリング、③晩期障害の発生に備えた治療終了後のフォローアップの3点が強調されている。
アントラサイクリン系薬剤によるがん治療関連心機能障害(CTRCD)の特徴は蓄積性かつ用量依存性であることである。例えばドキソルビシンでは500mg/m2が累積上限量とされている。しかし、郡司医師はより少ない累積量から注意する必要性があると強調した。「添付文書では500mg/m2を累積上限量としているが250mg/m2を超えると一気に心毒性の発症率が上昇するとの報告もあり、ASCOなど海外のガイドラインでは250mg/m2を累積上限量としている例が多い」と指摘した。さらに累積上限量は年齢や基礎心疾患の合併や既往、高血圧や喫煙歴などの心血管リスクの合併により変動することが知られているが、胸部縦郭などへの放射線照射でも変わる。
アントラサイクリン系薬剤の心毒性については通常の心不全と同様にアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬/アンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)やβ遮断薬が投与される。問題はそれら心保護剤開始のタイミングだ。「治療後からCTRCD診断が遅くなるほど心保護剤を開始しても心機能回復が見込め難くなる」と郡司医師は指摘する。
特に、CTRCDによる左室駆出率(LVEF)の回復傾向はCTRCD発症後の時間の経過とともに低下し、6ヵ月を過ぎるとほとんど回復しないとの報告を引きながら、郡司医師は「CTRCD発症後6ヵ月がpoint of no returnになる」と語った。心保護剤に反応しない群では有意に心不全による入院、不整脈や突然死が多くなる。LVEFが低下する前に早期心機能障害を検出するため、心筋トロポニンなどのバイオマーカーの上昇の確認やGLS(global longitudinal strain)などの検査の重要性を同医師は訴えた。
免疫関連心筋炎に対するアバタセプトの検証が進む
劇症型心筋炎は免疫チェックポイント阻害剤(ICI)の使用に対して最も警戒を要する有害事象だ。国立がん研究センター東病院循環器科の田尻和子科長は、近年活発化しているICIの適応拡大に触れ、「アジュバント治療など長期生存や治癒が望める患者にも適応が広がっており、心筋症に対する特段の注意が必要」と語った。
ICIの使用によって引き起こされる自己免疫反応が関与する副作用を免疫関連有害事象(irAE)というが、irAE心筋症の発症率は1%とそれほど高くないが、一度発症した際の致死率は25~50%と高い。田尻科長は「最近になってirAE心筋症の危険因子が明らかになってきた」と語った。がん治療に伴い起こった心筋炎に感作されたT細胞が体内に残留し、そこにICIの治療が行われることにより、それらT細胞が活性化することによって引き起こされるという。健康な状態では行われている自己反応性T細胞の排除ができなくなっていることが危険因子になっているという。
心筋症の発症が認められたときの標準的な対処法はプレドニゾロン1~2mg/㎏投与の支持療法が中心だが、近年はアバタセプトによる治療を試みる研究が増えているという。アバタセプトは関節リウマチの治療薬で抗原提示細胞(APC)表面のCD80/86に結合することによって、CD28共刺激シグナルを阻害し、炎症を抑える。
現在、アバタセプトのirAE心筋症を対象にした2つのRCT(ランダム化比較試験)が進行中だという。1つはマサチューセッツ総合病院のグループが進める第III相試験のATRIUM試験で、10mg/kg用量のアバタセプトをランダム化後の0、1、14、28日後に投与し、MACE(心臓死、心室性不整脈、心不全、心原性ショック)を評価項目にアバタセプトの効果を検証している。もう1つが第II相試験のACHLYS試験で、10mg/kg、20mg/kg、25mg/kgの用量を設定し、至適投与量を探っている。評価項目はCD86受容体占有率(80%以上を想定)、LVEF、心トロポニンレベル、感染症となっている。田尻科長は「この2つのRCTによってアバタセプトの効果と至適用量が決定できる」と期待している。
HER2療法の進化に伴い継続的な監視が必要
2023年のガイドラインで『CQ3 心血管疾患の合併のあるHER2陽性乳がん患者に対してトラスツズマブおよびペルツズマブ投与は推奨されるか?』を担当した名古屋医療センターブレストセンター・乳腺外科の澤木正孝センター長は、「抗HER2療法では晩期障害への配慮が必要だが、そのために初期治療を軽いものにしてはならない」と強調した。CQ3に対するステートメントは「投与前の循環器医との協議と治療中のモニタリングを前提に、トラスツズマブおよびペルツズマブ投与を提案する」であった。
澤木センター長は「乳がんでは治療後10年を経過すると心毒性による死因が乳がん自体による死因を上回ることが知られている。しかし、治療が奏効した10年を経過したゆえの心毒性とみることができる」と強調した。
抗HER2療法が登場するまでHER2乳がんは予後が悪い部類に属した。トラスツズマブの登場によって、有効な治療法があるむしろ予後が良いがんへと好転した。同時に、それはHER2陽性乳がんの診療は長期的に継続されるべき医療であることを意味している。抗HER2療法は、抗体薬物複合体(ADC)などが登場し、より強力なものになってきた。同センター長は「今後のHER2乳がんの薬物療法もアドオン、アドオンが続くとみられる。研究費を獲得して、長期的な予後を調べ、情報を共有化するためのレジストリシステムの構築が必要な時期にきている」と提案した。
血液がん治療における血栓症治療のジレンマ
造血器腫瘍(血液がん)を専門とするがん研究会有明病院血液腫瘍科の丸山大部長(院長補佐)はがん関連血栓症(CAT)、とりわけ静脈血栓塞栓症(VTE)のマネジメントについて報告した。同部長によると、がん関連VTE(CA-VTE)には①患者側要因、②がん関連の要因、③がん治療にかかわる要因の3つの要因が多面的に連動していると指摘する。
患者側の要因としては性別や年齢がある。男性よりも女性のほうが、また年齢が高くなることがCA-VTEのリスクを高めることになる。がん自体による直接的な血小板-血液凝固系の活性化や炎症反応に伴う線溶系の抑制などもCA-VTEのリスク因子となる。さらにがん薬物療法や中心静脈カテーテル留置などに内皮障害への配慮をしなければならない。
また血栓塞栓症には直接経口抗凝固薬(DOAC)が用いられているが、CA-VTEについても同様の傾向が認められている。しかし、世界標準は低分子量ヘパリン(LMWH)であるが、「わが国ではオフラベル」(丸山部長)であり、エビデンスの蓄積が十分ではない。一方で造血器腫瘍では造血系に障害が出ることから易出血傾向が高まるために血小板輸血を実施するケースもある。DOAC服用が原因で粘膜病変から出血することもあり、CA-VTEには慎重なかじ取りが求められる。
さらに多発性骨髄腫(MM)ではより複雑なマネジメントを求められる。MMではがん化した形質細胞(骨髄腫細胞)が産生する異常な免疫グロブリン(抗体)であるM蛋白(モノクローナル蛋白)が認められる。このM蛋白には血液凝固を促す働きがある。さらに、MMの標準治療薬となっているプロテアソーム阻害薬のポマリドミド、免疫調整薬のレナリドミドには血栓形成を促す副作用がある。
このことからMMを含め造血器腫瘍の治療ではCA-VTEの予防が重要であるが、先行研究を調べても、「血栓塞栓症の臨床研究でOS(全生存期間)を調べた論文が少ない」と同部長は指摘した。「領域によってアウトカム評価に違いがあることから、その評価方法も含め研究方法の在り方を見直す必要性があり、腫瘍医と循環器医との密なコミュニケーションが重要」と語った。また腫瘍循環器全般にかかわる見解として「重要性を主張しているだけでは事態は進展しない。診療報酬上の加算を確保するための体制づくりについても議論していく必要がある」とも述べた。
分子標的治療薬の使用に伴う心電図異常
2023年版のガイドラインでは不整脈が取り上げられなかった。矢野教授は「次回の改訂にはぜひ不整脈を取り上げたい」と語ってきた。国立がん研究センター中央病院総合内科・循環器内科の庄司正昭医長はこの問題を論じた。
庄司医長はフィンランドで実施されたがんと心房細動との関連を調べた臨床研究から、「がん患者は心房細動を起こしやすい」と紹介した。特に心房細動のリスクを高める薬物に注意が必要としてその例にブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬で、わが国では慢性リンパ性白血病(CLL)とマントル細胞リンパ腫に適応をもつイブルチニブを紹介した。イブルチニブの心房細動は4~16%の頻度で起こると報告されており、特に高齢者ではそのリスクが高まる。心房細動では脳塞栓を予防するとの考えから抗凝固薬が使われることが一般的だが、イブルチニブの副作用には易出血性があり、「抗凝固薬の導入が難しい場合がある」という。
国立がん研究センター中央病院において、2016年4月から2019年3月までにイブルチニブを内服した20人をレトロスペクティブに調べたところ、2人に心房細動が認められていたという。患者の平均年齢は68.9歳で高血圧や糖尿病、脂質異常症などの循環器関連疾患に罹患している患者が多い年齢であり、イブルチニブを使用する場合には慎重なかじ取りが要求される。実際、2021年に報告されたイブルチニブ関連心房細動のリスク因子として、心不全、弁膜症、心房細動の既往、65歳以上、睡眠時無呼吸症候群、高血圧などが挙がっている(Archibald WJ, et al.: Ann Hematol. 100(1): 143-155, 2021)。これらのリスク因子はイブルチニブを使用していなくても心房細動のリスク因子といえるものばかりだ。
また庄司医長は、心電図異常であるQT延長症候群を起こしやすい抗がん剤として、三酸化砒素、アントラサイクリン、タモキシフェン、白金製剤、5-FUなどを挙げたが、「新しい治療薬の中にもQT延長症候群が出やすいものがある」と述べて、トラスツズマブ、ボリノスタット(HDAC阻害剤)、BRAF阻害剤のダブラフェニブとベムラフェニブ、エリブリン、ボルテゾミブ、フォスブレタブリン、トロメタミン、FLT3阻害剤のキザルチニブを挙げた。「QT延長症候群は致死性不整脈につながることがある。心電図で認めた場合にはしっかりケアしていく必要がある」と総括した。
矢野教授は、「ガイドラインの次回の改訂には不整脈についてはぜひ庄司先生に執筆をお願いしたい」と語り、シンポジウムを終了した。