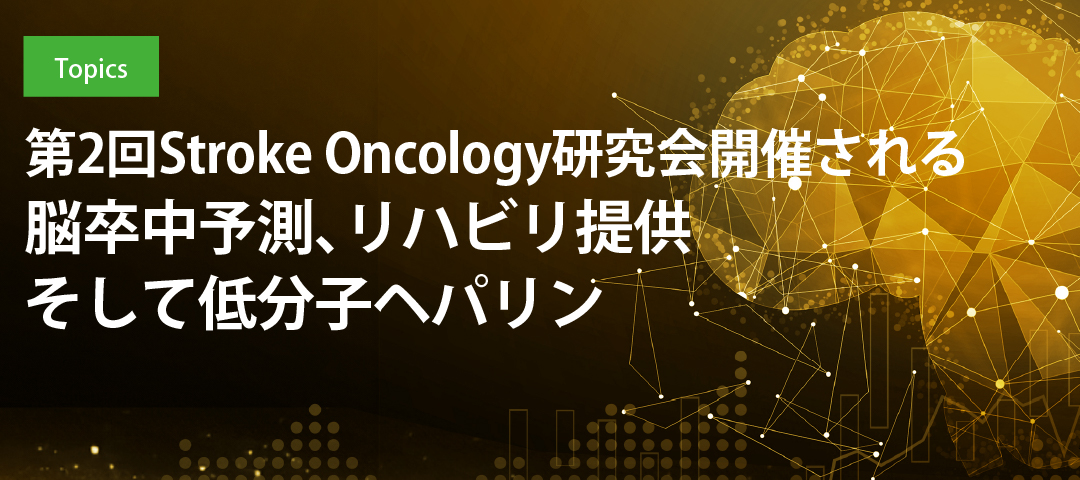がん診療と脳卒中診療という“異分野邂逅と学際探求”を目的に第2回Stroke Oncology研究会(腫瘍脳卒中研究会)が2024年12月21日に、都内で開催された(写真1)。がん患者の血栓回収療法やリハビリテーション治療とがん治療の両立など固有の問題が話し合われたが、研究会の発起人となった富士脳障害研究所附属病院院長の塩川芳昭氏は、同研究会の誕生が「日本腫瘍循環器学会の活動に触発された」と挨拶した。

- 写真1昨年の第1回に引き続き御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターを会場に開催

- 写真2「将来は学会となってガイドラインを作るという野望がある」と挨拶したがん研有明病院副院長の高野利実氏
「がん治療が進歩し、長期生存例が増えるにしたがって、さまざまな併発症の制御も無視できない問題になってきた。Stroke Oncology研究会はそのなかでも脳卒中とがんの併発という課題を討議する研究会。」第2回Stroke Oncology研究会の当番世話人を務めたがん研有明病院乳腺科部長で患者家族支援部長を兼任する高野利実氏は、研究会の冒頭、参加者を前にこう挨拶した(写真2)。
がん闘病中に脳梗塞や脳出血を発症する患者は決して珍しい事例ではなかった。がんも脳卒中も高齢者に好発する疾患であり、動脈硬化や慢性炎症など危険因子が共通している。その点では、脳卒中も心臓血液疾患も同様だ。これまでがんと脳卒中を併発する患者に対して積極的に対応する必要性について医療側は認識していたが、具体的な対応は後手に回ることが少なくなかった。
会の発起人となった塩川芳昭氏(前、杏林大学医学部脳神経外科教授)は「日本腫瘍循環器学会の初代理事長を務めた小室一成氏(国際医療福祉大学副学長)とは大学の同窓であり、日本腫瘍循環器学会の発足に刺激を受けて、日本脳卒中学会にタスクフォースを立ち上げたことが本研究会につながった」と研究会発足の経緯を語った。
研究会が取り組むべき重点事業

- 写真3新たに代表世話人に就任した杏林大学医学部脳卒中医学教室の河野浩之氏
昨年、第1回研究会を開催した塩川氏に代わって、今回からは杏林大学脳卒中医学教室准教授の河野浩之氏が新たに代表世話人を務めることが決まった(写真3)。河野准教授は基調講演の中で、「腫瘍脳卒中はさまざまな未解決課題を抱えている」と指摘した。
河野氏は、その具体例として脳卒中予測スコアの確立、抗血栓薬の低分子ヘパリンの活用、がん患者に対する血栓回収療法や血栓溶解剤であるtPAの使用、リハビリテーション治療とがん治療の両立、脳卒中患者を対象としたがんのスクリーニングなどを指摘した。さらに、これまで実施したアンケート調査や日本がんサポーティブケア学会との共同研究の結果を参考に、「Stroke Oncology研究会が今後取り組むべき重点事業」として①国内未承認の低分子ヘパリンの承認、②がん患者の脳卒中リスク予測の確立、③リハビリテーション提供に伴う問題点の克服の3点を挙げた。
腫瘍循環器学、運動腫瘍学などがんを核にした複数の学際領域と深くかかわる高野氏は、「日本腫瘍循環器学会はガイドラインを作成し、臨床研究にも注力し、エビデンスの収集を進めている。Stroke Oncology研究会もガイドラインの作成やエビデンスの創出、必要な保険診療への働きかけなどのためにも将来は学会となりたい」と語った。
がん医療と脳卒中医療の両立問題
Stroke Oncologyの領域で特に問題になるのががん治療と脳卒中治療をどのように両立させるかという問題だ。その象徴といっても良いのが、回復期リハでは診療報酬が包括となっているために、その間はがん薬物療法ができないという問題点が指摘されている。
また抗血栓療法に使われるヘパリンのうち、わが国では国際的標準となっている低分子ヘパリンが保険対象外という問題がある。腫瘍循環器では、DOAC(直接作用型経口抗凝固薬)が広く使われているが、脳卒中診療ではDOACの出血傾向が顕著に現れるケースが多く、低分子ヘパリンの承認を求める声も小さくない。日本腫瘍循環器学会でも低分子ヘパリンが保険で使用できないことを問題視しており、公知申請したが、認められていない。
こうした保険と日常診療の不整合について学会などが厚労省に要望しても「ガイドラインに記載されているか」と規制当局担当者からの質問が返ってくるケースが多い。塩川氏は「こうした問題を解決するためには研究会としてエビデンスを創出し、独自のガイドラインを作成し、そこに記載する努力が必要」と発言した。
またがんと脳卒中の併発は、患者や家族にとっても大きな重荷になる。経済的な困窮も加わり、家族が十分な当事者能力を発揮できない困難事例となるケースもある。研究会では、がん研有明病院でMSWを務める田近忍氏が、自身が経験した困難事例を報告し、「患者がどのように生きていきたいのか、家族を含めて話し合えるACP(アドバンス・ケア・プランニング)などを留意する必要がある」と訴えた。