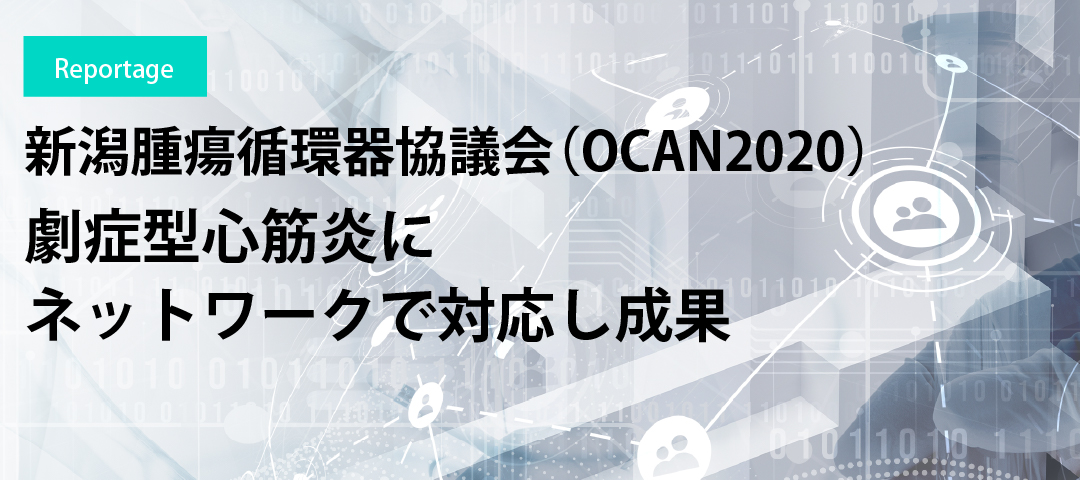人手不足が常態化している医療現場で新しいテーマである腫瘍循環器の問題に十分に取り組むことは容易ではない。特に免疫チェックポイント阻害薬による劇症型自己免疫性心筋炎となれば、その対応は一刻の猶予も許されない。新潟県ではこの問題を県内医療機関が参加した協議会で対応し、成果をあげている。
新潟県に住む60歳代女性Aさんは悪性黒色腫(Stage IIB)に罹患していた。患部は右足底。新潟県立がんセンター新潟病院の医師らが外科手術を実施、術後に免疫チェックポイント阻害薬(ICI)を含む、術後補助療法を開始した。最終投与を受けたときになって胸部不快感を訴えたため、同院が心精査を行った。最終投与から約1ヵ月後の夜間には動悸が出現。翌日に同院を受診し検査を行ったところ、心電図では持続性心室性頻拍を、心エコー図検査では高度左室性収縮不全を認めたことからICIによる劇症型自己免疫性心不全が疑われた。
即日、新潟市民病院へ転院し、後述するIMPELLA CPによる循環補助を開始、同日中に心筋生検による迅速病理診断を行った結果、リンパ球性心筋炎と確認された。そこで、定法に従い、ステロイドパルス療法を転院当日に開始、ICU管理とした。
幸いなことに左室収縮能は速やかに回復、4日後にはIMPELLA CPから離脱でき、1週間後には心エコー図検査で左室壁運動を確認した。さらに10日の入院の後、悪性黒色腫の治療を継続するために新潟県立がんセンター新潟病院へ再転院となった。
新潟市民病院高度先進医療センターの医師で、患者の治療に当たった尾崎和幸医師は「結果的にここが一つの分水嶺になった。患者救命の決め手になったのは発症翌日のこのがんセンターの医師の対応だった」と尾崎医師は指摘する。「患者は動悸を主訴に翌日、予約外でがんセンターを受診、主治医がトロポニンTの上昇に気がつき、心臓MRIを指示した。このがんセンターの医師の気づきが重要だった。また、本症例の転帰は一連の病診連携の成果であり、日ごろから医療機関の間でこのような症例の発生を想定していて、治療方針が各施設で共有されていたことで迅速な対応が可能になった」と述べる。こうした対応を可能にした背景には新潟大学の循環器内科、腫瘍内科が中心になって組織された新潟腫瘍循環器協議会(OCAN2020)の存在があった。循環器医として今回の症例の治療にあたった尾崎医師に詳しく尋ねることにした。
IMPELLA実施施設は県内2ヵ所

- 写真1新潟市民病院高度先進医療センターの尾崎和幸医師
今回、患者の救命に威力を発揮したIMPELLAとは、超小型のポンプを内蔵したカテーテル。経皮的補助人工心臓とも呼ばれ、重症心不全や心原性ショックを対象に2017年に保険適用となっている。保険適用になっているとはいえ、高額であり、扱いも複雑であることからどこの施設にもあるというわけではない。ましてやがん専門病院に設置されることはまずない。
新潟県はそうでなくても循環器医療の視点からは十分に恵まれた環境とはいえない。尾崎医師は語る。「県民人口に対して循環器医の数、ICUのベッド数では新潟県は全国47番目。IMPELLAを設置しているのは新潟市民病院と新潟大学医歯学総合病院の2ヵ所しかない。IMPELLAの絶対数が十分でないとなれば、もっている施設ともっていない施設間のコネクション、言い換えると情報を即座に共有できるネットワークの整備が重要になる。」
限られた医療資源を有効活用するためにはまず、県内の腫瘍医と循環器医との間で知識と情報を共有する必要があった。「心筋症に対応するためには意思決定のタイミングが最も重要。特にICI関連心筋症(irAE心筋症)の場合は初動が特に大事。」(尾崎氏)
「とにかくスタートすることが大事」
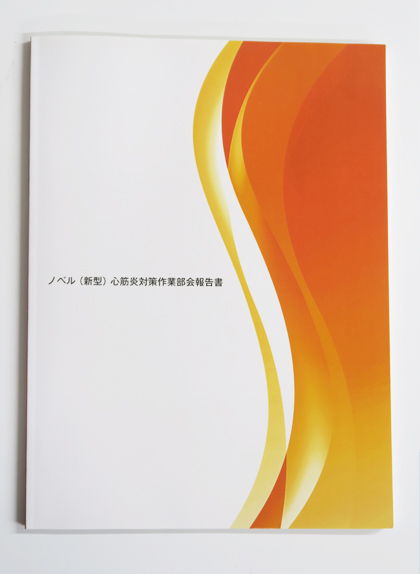
- 写真2『ノベル(新型)心筋炎対策作業部会報告書』の表紙。2023年1月23日発行。ノベル(新型)心筋炎対策作業部会著、新潟県立がんセンター発行
2010年代中頃から、がんやがん治療に伴う循環器障害が注目され始めた。しかし、この分野は未熟であり、症状が発現した際の対応もあいまいだった。尾崎医師は「しかし、潜在的な対処の必要性は多くの医師が感じていた」と話す。そこで、腫瘍医と循環器医の間で交流の場を作ろうという動きが始まった。そこには、新潟県には大学病院が新潟大学医歯学総合病院しか存在せず、県内の病院のほとんどが関連病院。医師の多くが同窓生という風土も幸いした。しかし、組織化に向けて背中を押したのが2017年の日本腫瘍循環器学会の発足だったという。2020年に新潟腫瘍循環器協議会として発足、定期的にセミナーを開催するなど知識や情報のアップデートに努めている。
さらにその成果を、かかわった医師らが分担して報告書にまとめた。タイトルは『ノベル(新型)心筋炎対策作業部会報告書』(写真2)。尾崎氏は「この報告書を作成、共有していたことが症例の早期発見と迅速な転院および早期治療につながった」と語る。
報告書は、新潟大学、新潟県立がんセンターの医師らを中心に県内の医師と薬剤部、看護部、検査部のスタッフが協力してまとめたもの。がん治療病院、救急病院、教育・研究機関、医師会の各ステークホルダーの観点から「目標」「問題点」「対応」を討議して、まとめている。解説書であると同時に救急時のマニュアルにもなっている。
ICIがもたらす心筋症の心電図、心エコー図、MRI画像などの病理の丁寧な解説に加え、実際に症例が発生した場合の新潟県内の救急体制までもが説明されている。
協議会が掲げる重点目標
- アントラサイクリン心筋症・心不全の早期発見と治療
- Cancer-VTEの予防と早期発見と治療についての体制作り
- HER2阻害薬等による心毒性の登録調査と治療法の確立
- 免疫チェックポイント阻害薬による心筋炎の登録調査と治療法の確立
ミーティングを重ねて、知識が蓄積したことから、各専門家が分担執筆した冊子を作成、県下の関係医療機関に配布した。尾崎医師は指摘する。「とにかく組織をスタートさせることが大事だ。これまでの教訓は正しく判断し、迅速に動くこと。これが何より大事だ。今動かなければ患者の命を救えないというタイミングも存在する。対応が1日遅れれば心臓以外の臓器の障害も進んで救命できないという状況もあり得る。とにかく自分が率先して動く必要がある。一方で医師の働き方改革に応える必要もあり、何でもかんでも1人で対応することはできない。情報を即座に共有できるネットワークを日ごろから構築しておくことが重要になる。」